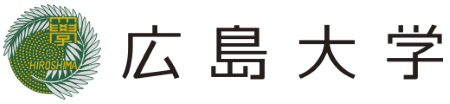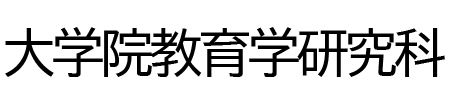研究者への道
名古屋学芸大学ニューマンケア学部 子どもケア学科 准教授 加藤 望
幼研での大学院生活を振り返って
私は中坪史典先生の研究室で、博士の学位を取得しました。入学前から保育者養成課程の教員をしていましたので、社会人としてフルタイムで働きながら、授業を履修したり研究のご指導をいただいたりという6年間でした。いかに時間を確保するかが日々の課題で、その結果、編み出した方法が、生活のルーティン化に伴う時間の断捨離と、ながら時間と隙間時間の活用です。例えば、買う物をいつも同じに(食材や日用品だけでなく、服や靴、ランチのパンまで!)したり、ヘアカットも短めオーダーで美容師に一任したりすることで、どれにしよう?と迷う時間を一切削りました。また、ドライヤーをかけながら文献を読む、料理の煮込み時間に仕事のメールチェック、子どもの習い事で送迎の待ち時間には車中やカフェで論文を執筆し、時間を二倍にして使いました。 名古屋在住で、頻繁に広島へ通うことはできませんでしたが、ゼミ活動にもたくさん参加させてもらい、久しぶりの学生生活も謳歌しました。ここに在籍していなければ、見ることのできない景色、感じることのできない気持ち、改めて理解できる幼児教育の素晴らしさをたくさん経験させてもらいました。そして生涯の友との出会いがありました。また、何より最先端の幼児教育について、質の高い保育実践について、質的研究の具体的な方法について、理解を深めることができました。学位授与式の日には、修了することを惜しく思ったくらい、私にとって幼研での大学院生活は有意義な時間でした。もちろん良いことばかりではなく、査読に落ちて悔しくて泣いたことも、厳しい指導をいただいて落胆したこともありますが、それらも含めて、映画の主人公のような、一生忘れられない時間を過ごさせてもらいました。
今、研究者として

今の私は、相変わらず、保育者養成課程の教員をしています。博士の学位を取得したことで、大学院の授業も担当することになりました。学会の理事や査読委員といったような仕事を依頼されることも増えました。その他、外から見る分には、以前と何も変わらない私です。
でも、中身は確実に変わりました。進学前は専門を聞かれると、遠慮がちに「幼児教育学です…」と答えていて、(おそらく「心理学です」とか「造形です」とかいう答えを期待されて)「その中でも専門は?」とさらに質問されると困ってしまい、「授業では保育原理を教えています」などと濁していました。それが今では、自信たっぷりに「幼児教育学です!」と答えられます。続く更なる専門についての質問にも、一時預かり事業をはじめとした、現在、研究している内容を詳しく話すと、興味を持って聞いていただけます。
「博士の学位は足の裏の米粒(取らないと気持ち悪いが取っても食えない)」と、誰かが言ったとか言わないとか、そんな言説がありますが、米粒を取った私の足の裏は、すっきりとして歩きやすい足です。大切なのは米粒の方(学位)ではなく、学位取得までをどのような足で歩んできて、これからをどんな風に歩んでいくのか、なのかもしれません。広島大学大学院で先生方のご指導の下に鍛えてもらったこの足は、なかなかの健脚ですから!山あり谷ありの研究者の道も、きっと着実に歩んでいけます。
比治山大学 現代文化学部 子ども発達教育学科 准教授 本岡 美保子
幼研での大学院生活を振り返って
私は,広島大学大学院へ入学してから7年間,幼年教育研究施設(幼研)に在籍し,博士課程を修了しました。入学1年目は子どもを育てながら保育の仕事もしていましたので,目がまわるような毎日を過ごしました。早朝からの家事と仕事に加えて観察研究,午後からは観察研究のまとめと授業への出席,夕方からは家事と授業課題に取り組む,というように。
右も左もわからずに入学して,追われるような日々を過ごしていた私とって,同期や先輩の姿はとても眩しく見えました。随分前に卒業した大学は教員養成系でしたが,日常でも当たり前のように使われる専門用語や外来語がわからずに,あとからこっそり調べたこともあります。そんな私にも,幼研の皆さんは優しく接してくださり,いつの間にかたくさんの友人ができました。
研究というものの厳しさや難しさを知ったのも,この頃でした。子どもの姿を研究として書くことへの葛藤を抱いていた私に,指導教員の七木田先生がおっしゃった「腹を括ってください」という言葉は,今も胸に残っています。特別研究という授業では中坪先生にもご指導いただき,杉村先生や清水先生にも総合特研という授業で研究のアドバイスを数多くいただきました。先生方のご指導のもと,次第に私は研究の楽しさも感じるようになりました。私にしかわからない,子どもとの関係の中で生じた現象の意味を,研究として残していきたいと強く思うようになりました。その気持ちは保育者をやめた今でもありますが,これからは私以外の保育者の方々と子どもとのやりとりからも,研究をさせていただきたいと思っています。
現在の職場に生かされていること

私は現在,比治山大学現代文化学部子ども発達教育学科で,保育者養成をしています。保育内容総論,保育原理,乳児保育,実習指導といった保育の中核を担う科目を担当させてもらい,責任とやりがいを感じています。教科書に書かれている以上のこと,例えば最近の研究成果や海外の保育の動向,実際の子どもの姿だけではなくその意味などを学生に伝えることができるのは,幼研に在籍していたからだと思います。
学生には常々,いつも心を輝かせていてねと言っていますが,それは私が幼研で目にした,研究に日々打ち込んで輝いていた先生や先輩の姿そのものです。幼研の先生や先輩をお手本に,私自身も心を輝かせながら,研究や教育活動に邁進したいと思います。
島根県立大学短期大学部保育学科 藤 翔平
幼研での大学院生活を振り返って
私は、大学・大学院の計10年間広島大学に通い、幼年教育研究施設(幼研)には学部3年から約7年半もの間お世話になりました。指導教員の杉村 伸一郎先生には、研究をする能力だけではなく、研究者としての在り方や社会人として必要な心構えや態度も教えていただいたように思います。また、副指導教員であった清水 寿代先生、幼児教育の観点からご指導いただきました七木田 敦先生、中坪 史典先生からも貴重なご指摘をいただくことが多く、今の研究に活きている部分が多くあります。 博士課程後期を修了し幼研を離れてから、幼研という教育研究機関の貴重さをひしひしと感じます。心理学と教育学という異なる研究分野が共存していること、森の幼稚園である広島大学附属幼稚園との強い結びつき、中国人留学生や社会人院生のように国や年代を超えた交流ができることなど、幼研の素晴らしさを挙げるときりがありません。 そういった貴重な環境に、研究生活の序盤に巡り会えたことはとても幸運なことでした。幼児の心理や教育に興味があり、その興味関心を研ぎ澄まし究めたいと考えている方がおられましたら、幼研に是非いらしてください。おそらく、求めているものはそこにあると思います。
現在の職場について
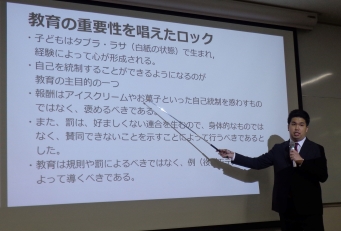
私は現在、島根県立大学短期大学部保育学科で助教をしております。島根県立大学短期大学部保育学科は、島根県を中心として多様な学生を募り、2年間保育者としての専門性を高めた後、山陰各地に保育者を送り出すという島根県および山陰の保育を支える教育機関です。今は発達心理学、幼児理解と教育相談、幼児理解の方法、保育実習IA指導、卒業研究といった科目を担当しています。
幼研に在籍している時には、先輩や先生方から専門学校や大学で授業する機会を頂くことが多くありましたので、授業経験に困ることはほとんどありませんでした。また、附属幼稚園を始めとした保育施設と関わることも多くありましたので、保育実習についても違和感なく担当できているように思います。そして、杉村先生を始めとした幼研の先生方の親身な指導は、学生の研究や進路を指導する際のモデルになっています。
今はまだ研究者としても、教育者としても幼研の先生方の足元にも及びませんが、一日一日を大切にし、少しでも先生方のような素敵な先生になりたいと思います。
ソウル神学大学校保育科 教授 玄正煥
幼研での大学院生活を振り返って
私は1989年幼研の博士課程の第1期生として入学し、1993年3月修了と同時に本国(韓国)に帰りました。4年間の幼研での生活は、人生のどの時期よりも私の価値観や研究者としての心構え、研究力などに最も影響を与えた時期だったと思います。 幼研での大学院生活を振り返ってみますと、何よりも先生たちの顔が浮かび上がります。私の指導教官であった祐宗先生の仕事への情熱と研究へのエネルギーは決して忘れることができません。懇親会の時に"ほうれん草をよく食べるように"と学生たちにおっしゃった森先生のお話は今も心に刻んでおり、うちの学生たちにもたまに心の戒めとして言っています。幼児保健学演習の授業では"あなたの話は何を言ってるのか全然わからない"と言われたことで、清水先生はちょっとコワイなという感じもありますが、お会いしたいですね。子どもの社会性について共同研究もさせていただき、広島へ帰る時の汽車の中でいろいろな話をしながらまるで友だちのように私に接してくださった山崎先生に感謝の気持を感じています。いつも心優しく接してくださった鳥光先生や井上先生にもありがたく思っています。同期である湯澤先生と七木田先生の卓越な研究力にはいつも感心し、私はいくら努力すればあ~なれるかなと思ったこともあります。今考えてみると、当時先生たちをはじめ、同期や後輩たちの支えなしでは日本での博士課程を修了することができなかったと思います。その恩返しをしなきゃと思うこのごろです。韓国へいらっしゃる時は是非ご連絡ください。有益な訪問になるようにできるだけの協力をします。
韓国での生活

1993年3月に博士課程の修了と同時に韓国へ帰国し, 非常勤4年の過程を経て97年の9月に今の学校(ソウル神学大学校)に就きました。学校の歴史は2011年に開校100年になるくらい割合と長いですが、その規模は8つの学科と大学院を含めて4千人の学生を越えない小さいです。私の所属している保育科は280人の学生(一学年70人)がおり、ほとんどの学生は卒業後保育士を目指して勉強しています。私の担当科目は、心理学概論、幼児心理学、児童臨床心理学、カウンセリング心理学などを主に教えています。最近の学生たちは児童臨床に関心を持ち、卒業後は保育士以外に児童臨床心理士になりたがっている人も多くなっています。